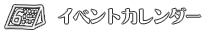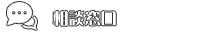本文
児童手当
請求(受給)者
児童手当は、高校修了までの年齢の児童を養育し、その家計を維持する方であり、日本国内に住所がある方です。
住民登録をしている市区町村に申請をしてください。公務員の方は、職場に申請してください。
夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。
対象児童について
高校修了までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)
※4月1日が18歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に18歳に到達し、その日が18歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
支給額について
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 0歳~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 0歳~3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
| 3歳~18歳未満(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳~18歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
- 金額は、児童1人当たりの月額です。
- 施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
- 第〇子とは、22歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの児童(親等に経済的負担がある場合)のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。
※4月1日が22歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に22歳に到達し、その日が22歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
所得について
・所得制限なし
所得判定時期
| 支給開始月 | 基準日 | 所得判定時期 |
|---|---|---|
| 1月~5月 | 前年の1月1日 | 前々年中の所得で判定 |
| 6月~12月 | その年の1月1日 | 前年中の所得で判定 |
認定請求書の提出について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。出生後または転入後15日以内に手続きしてください。(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。)
子どもが生まれたとき(第1子)
- 認定請求書 [PDFファイル/112KB]
- 請求者本人名義の通帳
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
転入するとき
- 認定請求書 [PDFファイル/112KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/63KB]
- 請求者本人名義の通帳
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
※監護相当・生計費の負担についての確認書については18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様を養育しており、お子様が3名以上いる場合に提出が必要です。
養育している児童と別居している場合
- 認定請求書 [PDFファイル/112KB]
- 別居監護申立書 [PDFファイル/33KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/63KB]
- 請求者本人名義の通帳
- 請求者、配偶者及び養育している児童の個人番号がわかるもの
※監護相当・生計費の負担についての確認書については18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様を養育しており、お子様が3名以上いる場合に提出が必要です。
額改定届の提出について
出生などにより支給対象となる児童が増えたときなどです。出生届を提出されただけでは児童手当の額が増額にはなりません。出生後15日以内に額改定認定請求の手続きをしてください。額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
子どもが生まれたとき(第2子以降)
受給事由消滅届に提出について
下記の事由に該当する場合、受給事由消滅届の提出が必要です。
- 受給者が日本国内に住所を有しなくなった
- 受給者が他の市町村に転出した
- 受給者が児童と別居することとなった(単身赴任の場合を除く)
- 受給者が公務員になったとき